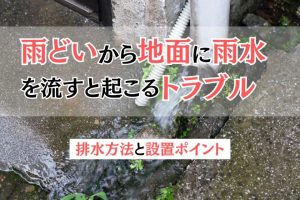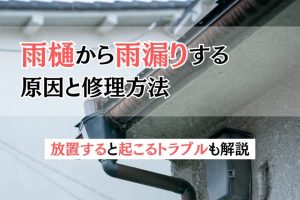雨樋はなぜ必要?役割を解説!形と素材の種類・メンテナンス方法も
雨樋

雨の日、屋根から流れる雨水を受け止めて排水する「雨樋(あまどい)」は、住宅の保護に欠かせない存在です。雨樋がなければ、外壁や基礎に水が跳ね返ってしまい、ひび割れやカビ・腐食といった劣化の原因になりかねません。また、騒音や雨漏りといった住環境の悪化を招くこともあります。
当記事では、雨樋の基本的な役割から形状や素材の種類、また長く快適に使うためのメンテナンス方法までを分かりやすく解説します。住宅を長持ちさせたい方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事はこんな方におすすめです】
- 雨樋の交換や修理を検討している方
- 自宅の外装メンテナンスを検討している方
- 雨漏りや外壁の汚れが気になっており原因を探している方
雨樋の役割とは?
雨樋(あまどい)とは、屋根に降った雨水を集めて地上や排水設備へと流すために設置されている筒状の部材です。住宅の外観にも影響する部材であり、建物の保護においても重要な存在です。
ここでは、雨樋が具体的にどのような役割を果たしているのかを詳しく解説します。
雨漏りの防止
雨樋の設置は、建物の雨漏りを防ぐ上で重要な役割を担っています。屋根に降った雨水は雨樋によって集められ、地上や排水設備へと効率的に流されます。雨樋がない場合、雨水は直接外壁や屋根のつなぎ目を伝って流れ落ちることになり、シーリングの劣化箇所や外壁のひび割れから室内に水が浸入し、雨漏りの原因となります。
特に軒の出がない住宅では屋根と外壁の境目が風雨にさらされやすく、雨樋がないと雨水の侵入リスクが格段に高くなります。雨樋を適切に設置することで、こうした浸入経路を遮断し、長期的に建物の耐久性を維持することが可能となります。
外壁や基礎の保護
雨樋は屋根から流れる雨水を制御し、建物の外壁や基礎部分を保護する働きも果たしています。雨樋を通さずに雨水が外壁を伝ってしまうと、外壁にコケやカビが発生しやすくなり、経年による劣化を早めてしまいます。また、跳ね返った雨水が基礎部分に継続的に当たると、土台の木材が湿気を含みやすくなり、腐食やシロアリの被害につながるおそれもあります。
特に日本のように雨の多い地域では、基礎のコンクリートに染み込んだ水分が内部にまで影響を及ぼし、建物全体の耐久性に関わるリスクとなりかねません。雨樋を正しく整備することで、外壁や基礎のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
騒音の対策
雨の日に「ポタポタ」という雨水の音が気になった経験がある方も多いのではないでしょうか。雨樋には、このような不快な雨音や雨だれの騒音を抑える役割もあります。雨樋が適切に機能していれば、屋根に落ちた雨水はスムーズに縦樋を通って排水されるため、途中で垂れることがなく、音の発生を抑えられます。
一方で、雨樋が破損していたり、詰まりが生じていたりすると、水が溢れて建物の金属部分やカーポートの屋根などに直接落ち、騒音の原因になります。雨が落ちる音が自宅だけでなく、隣家への騒音トラブルに発展するケースもあります。特に夜間や早朝は音が響きやすいため、雨樋による騒音対策は近隣環境への配慮としても重要な役割を担っています。
雨樋の形と素材の種類

雨樋にはさまざまな形状と素材があり、それぞれに特徴や適した用途があります。建物のデザインや環境条件に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。以下の表で、代表的な形と素材の種類をまとめました。
| 形状 |
|
|---|---|
| 素材 |
|
以下では、それぞれの形状や素材の特徴について詳しく解説します。
雨樋の形の種類
雨樋には複数の形状があり、それぞれに排水性能や外観、メンテナンス性などの特徴があります。以下の表で代表的な形の種類と特徴を確認し、それぞれの違いや適した用途を把握しておきましょう。
| 形状 | 特徴 |
|---|---|
| 丸型(半円型) | 最も一般的な形状で、構造がシンプルなため取り扱いやすく、価格も比較的安価です。 |
| 角型 | 水の流れる量が多く、デザインもすっきりしているため、都市部の住宅などによく使用されます。 |
| 意匠型 | デザイン性を重視した形状で、高級感があります。部品の互換性が少ないため、将来的な交換には注意が必要です。 |
| 内樋型(箱樋型) | 屋根の内側に設置するタイプで、外観がすっきりします。ただし、詰まりがあると雨漏りにつながりやすいため点検が重要です。 |
| リバーシブル型 | 丸型と角型の特性を兼ね備えた形状で、外観と排水性能のバランスを重視したい方に適しています。 |
| 特殊型 | 降雪地域向けの形状で、積雪による破損を防ぐための工夫がされています。非降雪地ではあまり採用されません。 |
丸型は取り扱いが容易でコストを抑えたい方に人気です。一方、角型は排水量が多く近年の豪雨にも対応できる実用的な形状です。意匠型や内樋型は外観の美しさを重視したい場合に向いていますが、メンテナンスの手間や費用がややかかります。設置環境や目的に応じて、最適な形状を選ぶことが大切です。
雨樋の素材の種類
雨樋には複数の素材があり、それぞれ価格・耐久性・施工性に違いがあります。以下に代表的な素材とその特徴を表にまとめました。
| 形状 | 特徴 |
|---|---|
| 塩化ビニル製 | 軽量で安価、施工しやすく錆びませんが、紫外線や熱に弱く、経年劣化しやすい素材です。 |
| ガルバリウム鋼板 | 錆びにくく耐候性があり、金属の中では比較的安価ですが、塗装によるメンテナンスが求められます。 |
| 銅製 | 美しい外観と長寿命が特徴で、酸化による緑青も魅力ですが、非常に高価で穴あきのリスクがあります。 |
| ステンレス・アルミ製 | 錆びにくく耐久性に優れていますが、価格が高いため、一般住宅よりも工場や商業施設での採用が多いです。 |
雨樋のメンテナンス

雨樋は屋根から落ちる雨水を効率よく排水する重要な設備ですが、落ち葉や土ほこりなどのゴミが溜まりやすく、定期的なメンテナンスが必要です。詰まりや破損を放置すると、雨漏りや外壁の劣化につながる恐れがあるため注意が必要です。以下に主なメンテナンス方法をまとめました。
■落ち葉やゴミの除去
雨樋の詰まりは雨水の逆流やあふれの原因になります。年に1~2回を目安に、定期的に清掃することが大切です。
■破損やひび割れの確認
樋にひびが入っていたり継ぎ目が外れていたりする場合、早めの補修が必要です。放置すると水漏れや騒音の原因になります。
■傾きや歪みのチェック
雨樋が傾いていると排水がうまくできず、水が溜まってしまいます。水平器などで勾配を確認し、必要に応じて修正します。
なお、雨樋の点検・修理は高所作業を伴うため、事故のリスクもあります。作業は必ず専門業者に依頼し、安全かつ確実に対応するようにしましょう。
まとめ
雨樋は、屋根に降った雨水を集めて地上や排水設備に流すことで、建物を雨水の被害から守る大切な設備です。雨漏りの防止だけでなく、外壁や基礎の劣化を抑える効果や、雨音などの騒音を軽減する役割も果たしています。雨樋には半円型・角型などの形状があり、素材も塩化ビニル製・ガルバリウム鋼板・銅製など多様です。それぞれに特徴があるため、建物の構造や目的に合わせたものを選定しましょう。
また、雨樋は屋根からのゴミを受けやすいため、詰まりや破損を放置すると排水不良による雨漏りや、外壁の腐食、基礎の劣化を引き起こすリスクがあります。定期的なメンテナンスとして、ゴミの除去・破損の確認・傾きのチェックを行い、異常があれば早めに専門業者へ依頼することが、建物の長寿命化につながります。
この記事の監修者情報
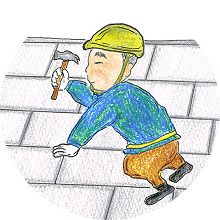
峠元 聡良
所属:峠元板金工業所
経歴:職人歴4年