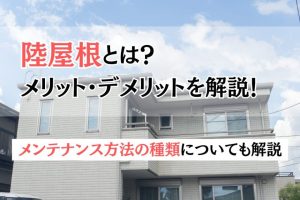神社では瓦がほとんど使われない理由2つ|屋根材の特徴も解説
屋根

神社建築といえば、独特の屋根構造が目を引く要素の1つです。しかし、一般住宅やお寺に多く使われる瓦は、神社ではあまり用いられていません。代わりに、檜皮葺きやこけら葺き、茅葺きなど、伝統的で自然素材を活かした屋根材が多く採用されています。
当記事では、神社で瓦が使われにくい背景をふまえ、よく使われる屋根材の特徴や実際に使われている瓦の種類について解説します。神社建築の屋根について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
【この記事はこんな方におすすめです】
- 神社建築に興味がある方
- 瓦と他の屋根材との違いを知りたい方
- 伝統建築の屋根材について学びたい方
目次
神社では瓦がほとんど使われない理由
日本の神社建築では、伝統的な景観や風格を大切にするために、瓦が使われることは非常にまれです。現代的な感覚では和風建築と瓦は切り離せない印象を持つかもしれませんが、神社においては異なる素材が選ばれるのが一般的です。
以下では、神社で瓦がほとんど使われない理由について2つ紹介します。
仏教建築と差別化するため
神社に瓦が使われない主な理由は、仏教建築との明確な差別化を図るためです。瓦屋根は、約1,400年前に仏教とともに中国から日本へ伝来しました。当時の瓦は素焼きで、主に寺院などの仏教建築に使用されていました。これに対して、神社は日本古来の神道に基づく建築様式を守る存在です。
神社建築では自然との調和を重視し、檜皮やこけらなどの天然素材が伝統的に用いられてきました。外来の宗教と結びついた瓦を避けることで、神道の神聖さや独自性を保ってきたと考えられています。宗教的背景に基づく意図的な使い分けが、現在でも神社に瓦がほとんど使われない理由とされています。
黄泉の国に神様がいることにならないため
土でできた瓦を使うと、神様が「黄泉の国(死者の国)」にいることになってしまうという考えから、神社では瓦が避けられてきたという説があります。
瓦は土を材料としてつくられる建材で、瓦屋根を神社に使用してしまうと「地の下(瓦屋根の下)に神様がいる」=「黄泉の国に神様がいる」という状態になってしまいます。そのため、神聖な存在である神様の住まいである神社に使用するのは不適切とされてきました。
神社建築では、神様を「天上」あるいは「高天原」にまつる存在と捉えています。その神様の社殿に、地中を連想させる素材を用いることは、神の位置づけと矛盾が生じると考えられてきました。
神社で使われている屋根材の特徴

神社建築には、日本古来の自然素材を生かした屋根材が数多く採用されています。見た目の美しさや神聖性の演出だけでなく、素材の入手や加工にも伝統技術が生かされているのもポイントです。
以下では、代表的な4種類の屋根材の特徴を紹介します。
檜皮葺き
檜皮葺きは、ヒノキの樹皮を少しずつ重ねて竹釘で固定する、日本独自の伝統的な屋根葺き工法です。668年に滋賀県の崇福寺で採用されていた記録があり、平安時代以降は最も格式高い屋根とされていました。神社や貴族の邸宅にも使用された歴史があります。
ヒノキは耐久性・防腐性に優れ、美しい曲線の屋根を演出できますが、施工には熟練の技術と多くの人手を要します。そのため現在では限られた社寺でのみ用いられており、代表的な例として出雲大社が挙げられます。費用面では1平米あたり約15万円と高価ですが、その分、重厚かつ優美な外観を実現できます。
こけら葺き
こけら葺きは、薄い木片(こけら)を何重にも重ねて施工する、日本古来の板葺き屋根工法の1つです。「こけら」とは木を薄く削った板を意味し、主にサワラやヒノキなどの軽くて耐久性に優れた木材が用いられます。
こけら葺きは飛鳥時代に始まり、平安時代には神社仏閣や貴族の邸宅に採用され、江戸時代に技術が完成されたとされています。高い通気性を持ち、湿気による腐食を防ぎながら、見た目にも繊細で優雅な印象を与えるのが特徴です。ただし、施工には高度な技術と多くの時間が必要となるため、現在では文化財など限られた建築物にしか使われていません。
茅葺き
茅葺きとは、ススキやヨシなどの茅(かや)を束ねて厚く重ね、屋根を覆う日本の伝統的な葺き方です。古くから農村部を中心に広まり、神社建築にも採用されてきました。断熱性・通気性に優れており、夏は涼しく冬は暖かいとされる屋根材です。
しかし近年では、茅の入手が困難になっていることや、葺き替えに高い技術と労力が必要なことから、施工できる職人が減少しています。このため、茅葺きの神社は年々減少し、文化財や重要な神社に限られる傾向にあります。維持管理の難しさが普及を妨げている現状です。
銅板葺き
銅板葺きとは、薄く加工した銅板を用いて屋根を覆う伝統的な屋根葺き技法の一つです。軽量で加工しやすく、耐久性にも優れているため、神社建築でも広く採用されています。檜皮葺きに比べて施工時間が短く、コストも抑えられる点が特徴です。
銅板屋根は、時が経つにつれて緑青(ろくしょう)という青緑色の錆が生じ、これが防錆効果をもたらします。ただし、異なる金属と接触すると腐食が進行する性質があるため、銅製や真鍮製のネジを用いるなどの工夫が必要です。
神社で使われる瓦の種類

神社では瓦が使用されることは稀ですが、近年では建築様式の多様化や耐久性の観点から、一部の神社で瓦屋根が採用される例も見られます。ここでは、実際に神社で使われることがある代表的な瓦の種類について紹介します。
日本瓦
神社建築では瓦の使用は少ないとされていますが、小規模な神社や地方の神社では日本瓦が使われることもあります。日本瓦は工事費が比較的安価で、平米単価は8,000円~10,000円程度です。
ただし、重量があるため地震や台風時の建物への負担が大きく、損壊リスクが高まる点には注意が必要です。また、沖縄の神社では伝統的に赤瓦が使われている例もあります。
ステンレス瓦
近年、神社の屋根材として注目されているのがステンレス製の瓦です。軽量で地震時の建物への負担が少なく、錆びにくく耐候性にも優れているため、長期間維持が求められる神社に適しています。
従来の銅板に代わって使用される例も増えており、実際に多くの神社で葺き替えに採用されています。ただし、平米単価は14,000円~16,000円程度とやや高額です。
まとめ
神社では瓦がほとんど使われない理由として、仏教建築との差別化と、土製の瓦が黄泉の国を連想させるという宗教的配慮があります。
代わりに檜皮葺き、こけら葺き、茅葺き、銅板葺きなど日本古来の自然素材が使用され、神道の神聖性と自然との調和を重視した建築様式が保たれています。近年は一部の神社で日本瓦やステンレス瓦も採用されていますが、伝統的な屋根材が主流となっています。
この記事の監修者情報
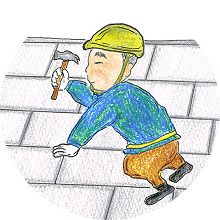
峠元 聡良
所属:峠元板金工業所
経歴:職人歴4年