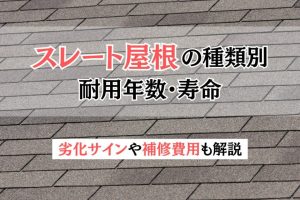屋根の棟(むね)とは?種類や役割・メンテナンス内容と費用を解説
屋根

屋根のてっぺんにある「棟(むね)」は、聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は雨風の侵入を防ぎ、屋根全体を支えるとても重要な部分です。新築や屋根のリフォーム、または定期的なメンテナンスを検討している方は、屋根の基礎知識を知っておくと業者と話すときに役立つでしょう。
当記事では、棟の役割や種類、修理・交換にかかる費用相場やメンテナンスのタイミングなどを解説します。屋根に関する不安や疑問がある方は、ぜひご覧ください。
【この記事はこんな方におすすめです】
- 屋根のメンテナンスについて詳しく知りたい方
- 屋根の劣化が気になり、メンテナンスを依頼するか検討している方
目次
屋根の棟(むね)とは?
屋根の棟(むね)とは、屋根の最も高い位置にあり、傾斜面が交わる頂点部分を指します。屋根の面と面が接する接合部であり、雨風が入り込まないようにするために、棟瓦などで丁寧に施工される重要な箇所です。
屋根の棟の種類と役割

屋根の棟は、屋根面と屋根面が交わる稜線部分を指しますが、場所によって「大棟」「降棟(隅棟)」「稚児棟」など名称が異なります。それぞれに役割があり、棟の形状や施工方法にも違いがあります。以下では代表的な棟の種類とその特徴を解説します。
大棟
大棟(おおむね)は、屋根の最も高い位置にあり、左右の屋根面が交わる水平部分を指します。棟の中でも中心的な位置にあり、屋根構造全体を安定させる重要な役割を果たします。また、雨水の侵入を防ぐため、防水処理や施工精度が特に求められる部分でもあります。
使用される建材や工法は屋根材によって異なり、瓦屋根では「のし瓦」や「丸瓦」などを重ねて固定する方法が一般的です。一方、スレートや金属屋根の場合は、「棟板金」と呼ばれる金属板でカバーされ、下地の貫板にビス止めされる構造になっています。
降棟(隅棟)
降棟(くだりむね)は隅棟(すみむね)とも呼ばれ、大棟から斜め下に向かって伸びる棟部分のことです。屋根の四隅に位置し、雨水を左右に分けて流す排水機能を担うと同時に、大棟から伝わる力を分散し、構造の安定にも寄与します。
瓦屋根では隅棟専用の棟瓦を使用し、勾配のある面にしっかりと施工する必要があります。ただし、斜めに設置される分、風や重力の影響を受けやすく、ズレや破損が起きやすい場所のため注意が必要です。劣化が進むと雨漏りの原因になるため、定期的な点検と早めの補修が求められます。
稚児棟
稚児棟(ちごむね)は、大棟から分かれるように設けられる短い棟で、主に屋根の意匠性や構造上の補助的役割を果たす部分です。寄棟屋根や複雑な形状の屋根に見られ、降棟や他の屋根面につながらずに途中で終わるのが特徴です。
稚児棟は、見た目のバランスを整えるために設けられることが多く、構造的な補強としての役割も担います。ただし、施工箇所が限られているため雨仕舞いが難しく、防水性や耐風性を高めるために丁寧な施工が求められる部位でもあります。
素材別|屋根の棟のメンテナンス
屋根の棟には、瓦屋根に使われる「瓦棟」と、スレート屋根や金属屋根に使われる「板金棟」があります。どちらも風雨にさらされるため劣化しやすく、素材ごとに適したメンテナンスが大切です。
以下では、それぞれの棟の特徴と主なメンテナンス方法について解説します。
瓦棟
瓦棟は風雨や地震の影響を受けやすい場所です。経年劣化により、棟瓦のズレや漆喰の剥がれ、内部の土の流出などが起きると、雨漏りや瓦の落下につながるおそれがあります。そのため、瓦棟には状態に応じた適切なメンテナンスが必要です。
以下に主な対応方法を整理しました。
| 内容 | 特徴・目的 |
|---|---|
| 漆喰の塗り替え | 経年でひび割れや剥がれが生じた漆喰を塗り直すことで、防水性と耐久性を回復させます。 |
| 部分補修 | ズレや浮きが軽度な場合に一部の瓦を外して調整し、再固定することで最小限の施工で被害の拡大を防ぎます。 |
| 棟の積み直し | 棟全体にズレや歪みがある場合、瓦を一度すべて取り外して再施工することで、構造の安定性と防水性を確保します。 |
| 葺き替え工事 | 棟だけでなく屋根全体が老朽化しているときに実施。新しい瓦や下地に交換することで、長期的な安全性を高めます。 |
板金棟
板金棟は、スレート屋根や金属屋根の棟部分に設置される金属製のカバーで、下地の「貫板(ぬきいた)」にビスで固定されています。軽量で施工性に優れる一方、風雨や経年劣化の影響を受けやすく、定期的なメンテナンスが重要です。特に、ビスの緩みや貫板の腐食が進行すると、棟板金の浮き・飛散・雨漏りなどのリスクが高まります。
| 内容 | 特徴・目的 |
|---|---|
| ビスの打ち直し | 緩んだビスを交換・増し締めすることで、板金の固定力を維持し、風による浮きや飛散を防ぎます。 |
| シーリング補修 | 接合部やビス穴まわりのシーリングが劣化した場合、再充填により雨水の侵入を防ぎ、防水性を保ちます。 |
| 板金の交換 | 板金が変形・腐食した場合に新しいものへ交換し、機能性と美観を回復させます。 |
| 貫板の交換 | 木製貫板が腐食・劣化している場合、樹脂製など耐久性の高い素材に交換し、長期的な安定性を確保します。 |
屋根の棟のメンテナンスをする目安と費用

瓦棟と板金棟に分けて、メンテナンスの目安と費用相場を紹介します。
■瓦棟のメンテナンス目安と費用
瓦棟は、施工後15〜20年程度で漆喰の剥がれや棟瓦のズレが見られることがあります。漆喰の塗り替えは比較的軽度な補修にあたり、費用は1mあたり6,000~8,000円程度が目安です。
一方で、棟のズレや歪みが大きい場合には、棟瓦をすべて一度取り外して再施工する「棟の積み直し」が必要になります。この場合、1mあたり10,000~17,000円程度が一般的です。屋根の全体的な老朽化が進んでいる場合には、葺き替え工事の検討も必要になります。
■板金棟のメンテナンス目安と費用
板金棟は、10〜15年程度でビスの緩みやシーリングの劣化、貫板の腐食が起こりやすくなります。軽度な補修(ビスの打ち直しやシーリング補修)であれば、全体で1万円〜3万円前後で済むこともあります。
しかし、板金の浮きや飛散、下地の貫板が劣化している場合は、棟板金の交換工事が必要で、1棟あたり10万円〜20万円程度が相場です。木製貫板から樹脂製貫板へ交換する場合は、耐久性が向上する分、費用もやや高くなります。
まとめ
屋根の棟は、住宅の防水性と構造の安定を支える非常に重要な部分です。しかし、普段は目に入りにくいため、劣化や異常に気づきにくいという特徴もあります。棟には「大棟」「降棟(隅棟)」「稚児棟」などの種類があり、それぞれの形状や役割に応じた施工・メンテナンスが求められます。
また、瓦棟と板金棟では、点検方法や補修内容、費用相場にも違いがあります。棟の劣化は放置すると雨漏りや構造トラブルにつながるため、症状に応じて適切に対応することが大切です。定期的な点検と正しい知識にもとづいた判断によって、屋根の安全性と住まいの寿命を守りましょう。
この記事の監修者情報
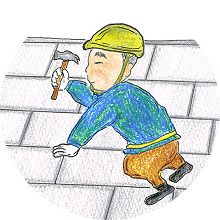
峠元 聡良
所属:峠元板金工業所
経歴:職人歴4年